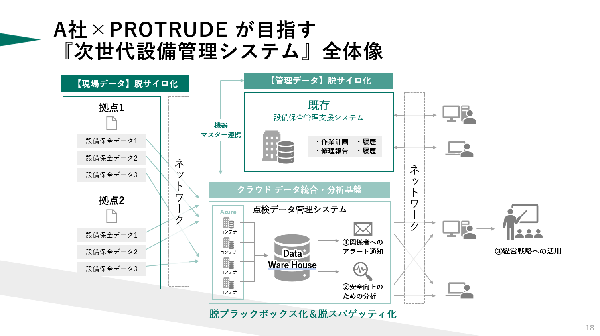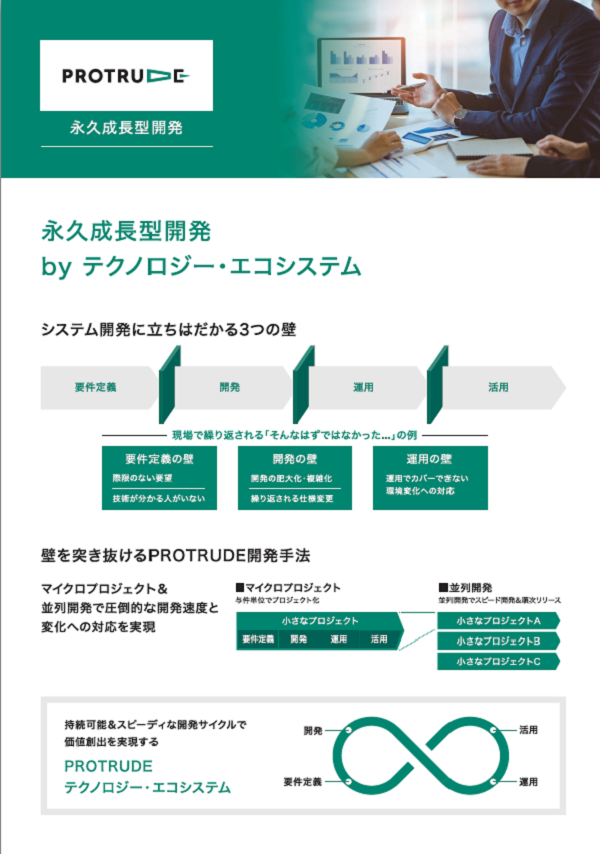PROTRUDE「Japan IT Week【春】」に初出展

Accelerate Your Future
Accelerate Your Future
Service サービス
デジタル変革を戦略設計から
運用改善支援まで一貫してサポート
インフラ基盤構築
基幹システム開発
アプリケーション開発
(WEB・モバイル)
WEBサイト構築
組み込み開発
ハードエンジニアリング
Feature サービスの特徴
循環型ソリューション
- 01
- 戦略立案から
改善支援までワンストップ
- 02
- 新規ソリューションの
発掘・導入支援


Capability 成功へと導く能力
- 01
- 25,000 名を超える専門人材
- 02
-
4,000
社を超える
企業現場の経験
- 03
- 71 の先端テクノロジー
Case Study 導入事例・実績
Case
株式会社協和日成
デジタル化とペーパーレス推進
アプリ開発でロスを削減
アプリ開発でロスを削減
業務ロスや提出の遅れを改善するため、運転日報のアプリ化に着手。RPA開発や、アプリの画面設計、承認ワークフローなどを作ることができる業務用開発プラットフォーム「Microsoft Power Platform」を活用した運転日報アプリを開発。
アプリの導入により、管理のデジタル化とペーパーレスを推進し、業務の効率化を実現。

| 流通・小売企業 |
|
|---|---|
| 通信系企業 |
|
| 金融系企業 |
|
| 情報系サービス企業 |
|
| 多数企業 |
|
| 通信系企業 |
|
|---|---|
| 外食・流通産業 |
|
| 自動車メーカー |
|
| 畜産業 |
|
| 多数企業 |
|
| 通信キャリア |
|
|---|---|
| 航空会社 |
|
| 鉄道会社 |
|
| 日系メーカー |
|
| ベンチャー企業 |
|